DAY3:2018年6月18日(月)その1
~陳麻婆豆腐店へ~
昨日は、李先生と方雷さんとの初対面でした。
初対面なのに何だか懐かしい気持ちがして、大いに語り合うことができました。

今日は、午後からの飛行機で上海に帰る日です。
午前に、どうしても行きたかった「陳婆さんの麻婆豆腐」店に行く予定です。

~因縁の「陳麻婆豆腐店」~
どうしても行きたかったというのは、2004年の因縁があったからです。
ぼくは、四川料理の中で、特に麻婆豆腐が好きです。
中国料理を食べる機会があると、ほとんどの場合、麻婆豆腐を注文するくらいです。
特に、本場四川の麻婆豆腐が好きです。
日本で食べる普通の麻婆豆腐は、山椒の香りがあまりしない物が多いですが、本場四川の麻婆豆腐は、山椒(さんしょ)がふんだんに使われていて、辛さより痺(しび)れ重視だと思います。
それがたまらなく美味しく感じてしまいます。
だから、2004年に「黄龍(こうりゅう)・九寨溝(きゅうさいこう)」の観光で成都に来た時、「陳麻婆豆腐店」で、ぜひ、食べたいと切望していました。
(「黄龍・九寨溝」の旅の様子については、後日、当ブログで紹介する機会があると思います)
でも、その時は、時間的に都合がつかず、食べるに至らなかったのです。
その時のガイドさんは、成都市内の観光をしている時、「陳麻婆豆腐店」の前を通り、
「ここが、かの有名な麻婆豆腐発祥の店、陳麻婆豆腐店です」
と説明だけして、通り過ぎたのです。
ぼくは、黄龍九寨溝に行くのを少し遅らせてでも食べたいと思いましたが、そんなわがままも、大人気(おとなげ)ないと思い、その時は、泣く泣く我慢したのでした。
だから、今回、せっかく成都に行くのだから、是非食べたいとYAさんにお願いしてありました。

発案した陳婆さんこと「陳劉氏」さんです。

発祥当時の店構えです。
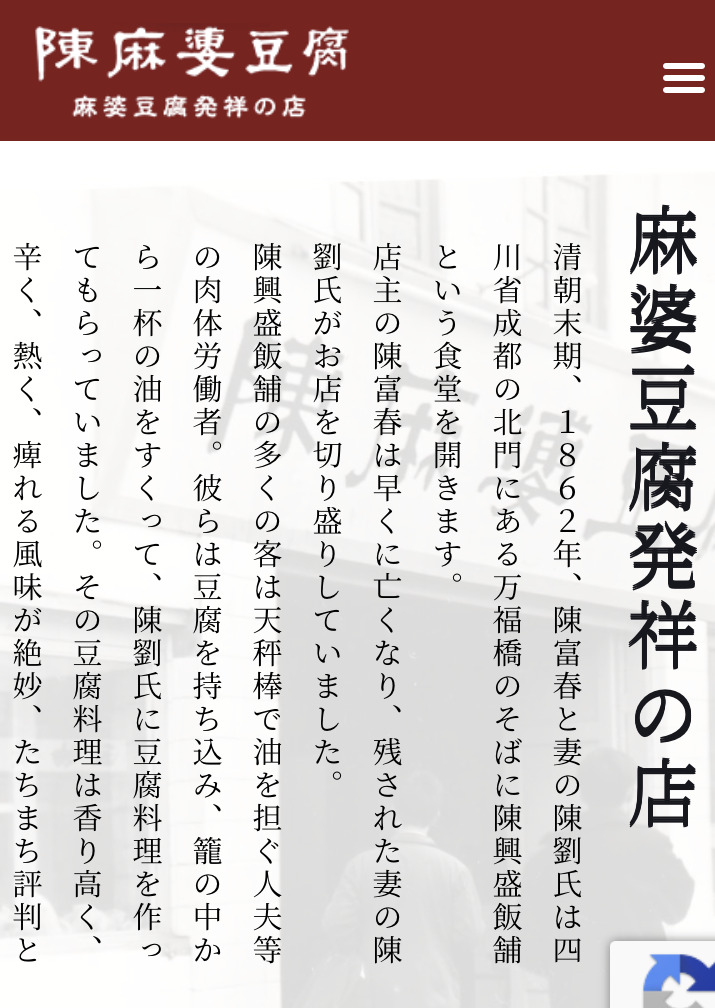
麻婆豆腐発祥の説明です。

「陳麻婆豆腐」の店内です。
思ったより店内は、広く、豪勢な造りです。

ふんだんに山椒の粉が、ふりかかっています。
豆腐、長ネギ、ニラ、挽肉とともに、山椒の実もかなりの量、入っています。
ぼくは、辛い物が大好物なわけではありません。
特に激辛料理は、得意ではありません。
汗が全身から噴き出して、サウナに入ったようになります。
この店の麻婆豆腐は、予想通り、激辛というわけではありませんでした。
赤唐辛子の辛さを抑えつつ、山椒の香りと痺れを前面に押し出した絶妙な味加減です。
長い年月、多くの人々から支持される理由が分かります。
~その他の四川料理~
その他の四川料理も少しだけ紹介します。

四川料理の代表、担担麺(たんたんめん)です。
ぼくも最初、日本の担担麺とのあまりの違いに、びっくりしてしました。
違う料理を頼んだのではないかと思うくらいです。
もともと、天秤棒を担いで、片側に湯を沸かすための七輪と鍋を、もう一方に麺や調味料、食器などをぶら下げて、肉体労働者たちに売り歩いたのが起源だと言われています。
担担麺の「担」は、担ぐという意味で、天秤棒を担いで作られた麺料理なので、「担担麺」という名前になったと言われています。
そんな状況で作られた麺料理なので、手間暇かけずに即、出せるような「汁なしの担担麺」になったのだそうです。

日本の担担麺は、赤唐辛子系の汁の中に、麺が浮かんでいます。
辛さが苦手な日本人にも抵抗なく食べられるように、胡桃(くるみ)などで赤唐辛子の辛みを抑えているお店が多いですね。
やはり、ラーメンから派生した食べ物というイメージですから、日本では、こうなりますよね。

ご存じ「棒棒鶏(ばんばんじー)」です。
これも四川料理を代表する一品です。

こちらもご存じ「回鍋肉(ほいこうろう)」です。
すでに日本料理の一部といっていいくらいですね。

「口水鶏(よだれどり)」です。
中国語で口水と書いて「よだれ」の意味です。
この料理を見るだけで、よだれが出ることから名づけられたと言われています。
四川料理の中では、日本人にそれほど馴染みがありませんが、ぼくは、なぜか、この料理が大好きです。
茹(ゆ)でた鶏肉を冷やして香辛料や薬味をたっぷりかけて食べる冷菜です。
辛みと酸っぱさが混じり合い、食べる前から「よだれ」が出ること請け合いです。
~古さと新しさが混ざる街「寛巷子(かんこうし)」へ~
四川料理を堪能した後は、成都の街を「ふらブラ」です。

YAさんが紹介してくれたのが、「寛巷子」です。

古い街並みの中にモダンなアートなどが入りこみ、大変人気のある街だそうです。
この日もたくさんの人で賑わっていました。

日本でいう「歩行者天国」です。
公安や警察が歩行者の交通整理をしています。

さすが、四川です。
赤唐辛子のカーテンです。
もともとは、農家の作業場などに吊るして干してあるものですが、この通りでは、アートになっています。

その脇には、乾燥した唐辛子を粉状に磨り潰す(すりつぶす)臼がありました。
観光客が、面白そうに作業をしています。

赤唐辛子をペースト状にする昔ながらの木製器具もありました。
棒についている小さなカウベルみたいな鐘の音が、チャリンチャリン鳴って、とても牧歌的な雰囲気を醸し出していました。

四川省の名物の一つ「川劇」の劇場です。
今回は、時間の関係で見ることはできませんでしたが、劇場前でこのような衣装で、客寄せをしていました。
ちなみに、川劇で最も有名な「変面」は中国の重要国家機密の一つで門外不出だそうです。

このお店は、まさに「変面」のお店だそうです。

日本人には、あまり馴染みがない「耳垢(みみあか)とり」の露天のお店です。
意外に気持ちよさそうですね。(笑)

日本でも、たまにお目にかかる「似顔絵描き」です。
「本人より若干、よく描くこと」が繁盛の秘訣だということは、万国共通のようです。(笑)

金属製のモニュメントかと思ったら、生身(なまみ)の人間でした。
動かないことが重要ですが、あまりにも動かな過ぎると気付いてもらえず、売り上げに影響するらしいです。
この2人は、適度に人間ぽさが出ているので、かなりの売り上げがあるようです。
料金箱には、たくさんのお金が入っていました。
植木鉢の影に飲み水が隠してあるのが、人間臭くてほのぼのしていますね。
きっと、観光客が途切れた時を見計らって、急いで水分補給するのでしょうね。
想像するだけで笑えますね。
~YAさんに感謝です~
短時間でしたが、とても楽しい成都市内の「ふらブラ」でした。
YAさんには、李先生への橋渡しをしてもらったり、交流がうまくいくように通訳をしてもらったりして、心から感謝です。
ぼくの教え子たちも李先生と交流ができたのも、YAさんのお陰です。
自分だけでは、今回のような旅は絶対に実現できません。
こんなにも素晴らしい企画をしてもらい、「非常感謝(フェイチャン・ガンシェ)」です。
ますます、中国人が好きになりました。
蘭州の帰りの高速鉄道で偶然、出会ったYAさんですが、今では、「老朋友(ラオポンヨウ):昔からの親友のような仲のいい友人」になりました。
(第8話:最終話、終わりです)
今回で「シリーズ14:念願のシルクロードの旅Part5:四川・成都編」は、終わりです。
次回からは、7月27日から出かける「ヨーロッパ一筆書きの旅」の準備などの進捗状況を紹介するシリーズに入ります。
どんなことを目指して、どんな旅にしたいのか、出発前に、少しだけ知っていただけたらと考えています。
引き続きのお付き合いをよろしくお願いいたします。